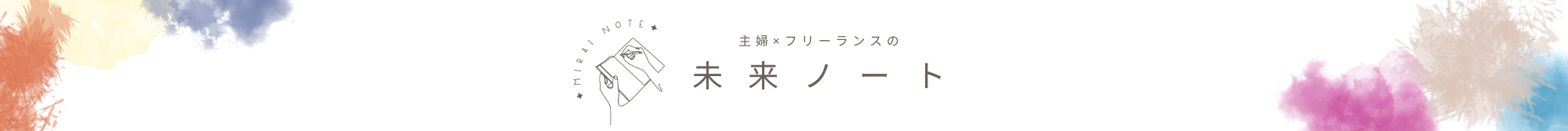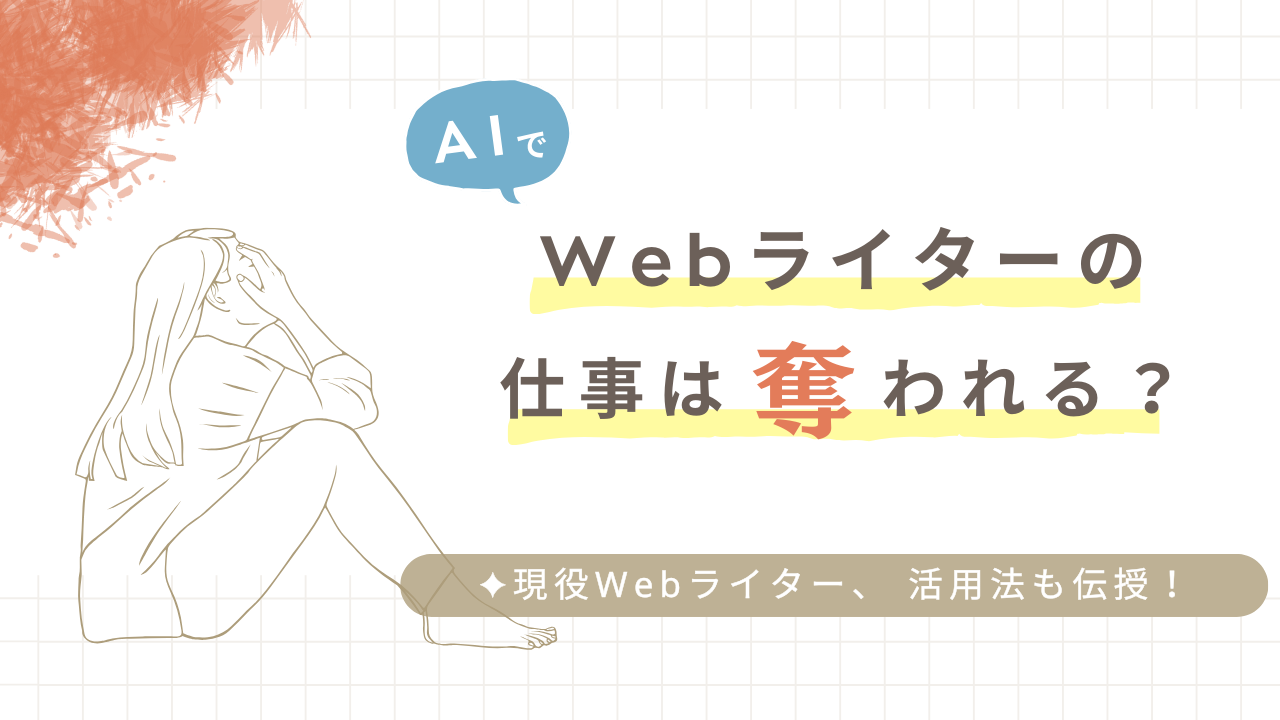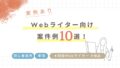「AIがWebライターの仕事を奪うのではないか…。」
そんな不安を抱えているWebライターの方も多いのではないでしょうか?
確かに、AIの進化によって基本的な記事作成はAIで可能になってきました。
その反面、人間らしい視点や専門性を持ったWebライターの需要はむしろ高まっています。
現役Webライターとして記事を執筆し、実際にAIツールを活用している私が、AIとWebライターの関係性を詳しく解説します。
この記事を読めば、AIを味方につけて仕事の効率を上げながら、Webライターとしての価値を高める具体的な方法が分かります。

AIと上手に付き合いながら、長く活躍できるWebライターを目指しましょう。
この記事で分かること
- AIがWebライターに与える影響
- AIを使ったWebライティングの方法
- AIと差別化したライティング方法
- AIを使ったWebライティングの注意
AIがWebライターに与える影響とは
近年、Webライターの間でAIの活用が広がっています。
業界に大きな変革をもたらすAIについて、以下の3つの観点から検証しました。
- AIによって変わるWebライティングの現場
- AIで失われる仕事と残る仕事
- AI時代に求められるWebライターのスキル
各項目の現状と課題を掘り下げながら解説を進めていきましょう。
AIによって変わるWebライティングの現場
最近は多くのWebライターが生成AIを使って、情報を集めたり文章を修正したりしています。
ライティングの見出しを考えるときも、キーワードを入れるとAIがいくつかの案を出してくれるので便利です。
実際に、以前は丸一日かかっていた記事が、半日で書けるようになったという声もあります。
しかし、AIに任せすぎると個性のない文章になってしまうので、上手に使い分けることが大切です。
AIで失われる仕事と残る仕事
基本的な説明記事や商品紹介記事は、確実にAIに置き換わりつつあります。
「○○って何?」といった解説記事や、「おすすめ商品ランキング」のような記事は、もうAIでも十分な品質で書けるようになってきました。
しかし、取材や体験レポート、専門的な技術記事、読者の気持ちに寄り添うコラムなどは、むしろ需要が増えています。





人間の経験や感情、専門知識が必要な分野では、AIではなく、Webライターの存在価値が高いですね。
AI時代に求められるWebライターのスキル
いまのWebライターに求められているのは、AIを上手に使いこなしながら、自分らしさを出せる力です。
まず大切なのは、AIツールを使いこなせることと、AIが作った文章を読みやすく編集できる技術。
AIに上手に指示を出す力や、生成された文章のチェック能力、専門的な情報を見極める目なども役立ちます。
また、クライアントと上手くやり取りする力や、魅力的な企画を考える力も大切です。
結局のところ、AIと人間それぞれの良いところを組み合わせて、より良い記事を作れる人が求められていくでしょう。
Webライターが活用すべきAIツール3選
WebライターがAIを活用する際に押さえておきたいツールを厳選。
以下の3つのAIツールの特徴を紹介します。
- ChatGPT
- Claude(クロード)
- Notion
実務での活用法から応用テクニックまで、段階を追って説明していきましょう。
ChatGPT
Webライターの作業効率を大幅に向上させる最も人気の高いAIツールがChatGPTです。
記事の構成作りから文章の校正まで、幅広い用途に対応した優れた文章生成能力が特徴。
毎月20ドルの有料プランでGPT-4が利用可能になり、より高度な記事作成をサポートします。
無料版のGPT-3.5と比べて、日本語の自然な表現力や情報の正確性が格段に向上しました。
記事のネタ出しでは、1つのキーワードから複数の切り口を提案。
さらに、執筆時には読者層に合わせた表現の調整や、専門用語の言い換えなども得意です。
Claude(クロード)
Webライターの業務で高い評価を得ているのが、Anthropic社開発のClaudeです。
日本語の理解力と表現力に優れ、長文の記事作成に強みを持つAIツールとして注目を集めています。
特にSonnetモデルは、専門的な内容でも読みやすい記事を生成できるようになり、多くのWebライターから支持を得ました。
記事作成では文脈を理解した的確な提案が可能で、見出しから本文まで一貫性のある構成を組み立てられます。
利用料金は月額課金制ですが、提供される機能と品質を考えると、プロのWebライターにとって十分な投資価値があるでしょう。





最新版は情報の正確性と文章の自然さが大幅に改善されていますよ。
Notion AI
Notion AIはWebライターの執筆環境を効率化する強力なツールで、記事の整理から執筆まで一括管理ができます。
Webライティングに特化した機能が充実し、チームでの共同作業もスムーズに進められる点が魅力です。
基本機能は無料で利用可能で、月に20回までAI機能を試せます。
また、有料プランは月額約1,400円からで、制限なくAI機能を活用可能。
記事の執筆では、文章の書き換えや要約、箇条書きへの変換など、多彩な編集機能を搭載しています。
AIを使ったWebライティングのメリット
Webライターの業務効率を大きく向上させるAIの活用について、以下の2つのメリットを紹介します。
作業効率が向上し時間短縮できる- 記事の構成やネタ出しが楽になる
AIを使ったWebライティングのメリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット①作業効率が向上し時間短縮できる
Webライターの作業時間は、AIの活用で大幅に短縮できます。
従来なら3時間かかっていた記事が1時間で完成することも可能です。
具体的には、記事のリサーチ段階でAIに情報を集めさせることで、検索時間を10分の1に削減できました。
また、記事の下書き作成にAIを使うことで、文章の組み立てにかかる時間も大幅にカット。
AIを使いこなすことで作業効率の向上により、新規案件の受注に対応できることで収入アップにつながりますね。
メリット②記事の構成やネタ出しが楽になる
AIを使ったWebライティングの中でも、記事のネタ出しや構成作りはAIの得意分野です。
1つのテーマから複数の切り口を提案してくれるため、Webライターの発想力を大きく補完してくれます。
例えば、美容系の記事を書く際にAIに相談すると、季節性やトレンド、年代別のアプローチなど、多角的な視点での提示も可能です。
さらに、各視点に合わせた構成案まで作ってくれるので、企画から執筆までの流れがスムーズになるでしょう。
WebライターがAIを活用し、作業量が増えることでクライアントからの評価も上がるケースが多いようです。





基礎のライティングができるからこそ活用できる部分もあるので、まずはスキルを磨くことが大切です。
AIを使ったWebライティングのデメリット
Webライターの立場からAIを使用する際の注意点として、以下の2つのデメリットが考えられます。
- 文章の個性がなくなる
- 情報が古い場合がある
具体的な対処法と併せて、デメリットを確認していきましょう。
デメリット①文章の個性がなくなる
AIを使ったWebライティングでは、文章に個性が出にくいというデメリットがあります。
例えば、多くのWebライターがAIの生成した文章をそのまま使用すると、どの記事も同じような表現や言い回しになってしまうのです。
具体的な例を挙げると、「~について解説します」「~が重要です」といった同じような表現が多用される傾向にあります。
実際にAIが生成する文章は機械的で画一的な印象を与えることが多く、読者の心に響きにくいという問題点があるでしょう。
AIが生成した文章をベースにしながら、独自の表現や経験談を織り交ぜることで、オリジナリティのある記事に仕上げていく必要があります。
デメリット②情報が古い可能性がある
Webライターがよく活用するChatGPTなどのAIツールは、学習データに制限があり、最新の情報が反映されないことが大きなデメリットです。
たとえば、2024年現在のChatGPTの場合、2022年以降の情報は含まれていないため、最新のトレンドや制度変更などを正確に把握できません。
また、AIが参照するデータの中には、誤った情報や古い規定が含まれている可能性も指摘されています。
以上のことから、専門的な内容や正確性が求められる記事では、必ず複数の情報源で事実確認を行う習慣をつけることが不可欠です。
特に、法律や制度に関する記事では、公式サイトや専門家の回答を確認して、最新の正しい情報を提供することが求められるでしょう。
生成AIを使ったWebライティングの具体的な手順
WebライターがAIを効果的に活用するための実践的なステップを確認しておくことが大切です。
以下の内容で生成AIを使ったWebライティングの具体的な手順を解説します。
- 記事のテーマを決めてAIで情報を集める
- AIに見出しと構成案を出してもらう
- AIを使って記事の下書きを作る
- 人間らしさを加えて記事を完成させる
では詳しく見ていきましょう。
①記事のテーマを決めてAIで情報を集める
記事のテーマが決まったら、まずChatGPTやClaudeにリサーチを依頼しましょう。
リサーチの際はWebライティングで解説したい内容を簡潔に伝え、具体的な指示を出すと良いでしょう。
ただし、AIが提供する情報は2023年以前のものが中心なので、必ず公式サイトや信頼できるメディアで最新情報を確認する必要があります。
AIを情報収集の入り口として活用し、人間が精査して記事の質を高めることがポイント。





収集した情報は箇条書きでまとめておくと、構成を考える際に役立ちますよ。
②AIに見出しと構成案を出してもらう
記事の構成はWebライターが最も頭を悩ませる部分ですが、AIに任せることで効率的に作成できます。
情報収集の段階で整理した要点を入力し、「目次(構成)を作成してください」と指示を出すのがおすすめです。
AIは過去の記事データを基に、読者が求める情報に対応した構成案を提案してくれます。
提案された構成は、クライアントの要望や自分の執筆スタイルに合わせて自由にアレンジしていきましょう。
最終的な構成は必ずWebライター自身が決定し、記事の独自性を保つことが大切です。
③AIを使って記事の下書きを作る
構成が決まったら、見出しごとに本文の下書きをAIに依頼しましょう。
AIに指示を出す際は「見出しの内容に沿って300文字程度の文章を書いてください」といった具体的な条件を設定すると良いでしょう。
生成された文章は表現が固くなりがちなので、一度別の言葉で言い換えるなど工夫が必要です。
また、読者目線で分かりやすい記事にするため、専門用語は極力避けて平易な言葉で説明するよう心がけましょう。





同じ質問でも回答内容に差があるので、気に入らない場合は何度か指示してみましょう。
④人間らしさを加えて記事を完成させる
AIが生成した文章は機械的な印象を与えがちなので、Webライターならではの視点や経験を加えることが大切です。
具体的には、実体験に基づく具体例の追加や、読者の疑問に寄り添った表現への書き換えなどが効果的でしょう。
また、段落の区切りを工夫したり、重要なポイントを強調したりすることで読みやすさも向上します。
最後に誤字脱字のチェックと事実確認を行い、人間が責任を持って記事を完成させることが重要です。
AI時代に生き残るWebライターになるために必要なこと
WebライターとしてAI時代に生き残るために必要なこととして、以下の3つが考えられます。
- AIと差別化する
- クライアントに選ばれ続けるポイント
- 今すぐできるスキルアップ方法
では、それぞれについて解説していきます。
AIと差別化する
AI時代に生き残るWebライターになるためには、オリジナリティの発揮が必須です。
例えば、自身の経験や専門知識を活かした記事作成は、AIには真似できない強みとなります。
実体験から得た気づきやノウハウは、読者の信頼性を高めるだけでなく、クライアントからの評価も上がるでしょう。
さらに、独自の切り口で記事を書くことで、AIが生成する画一的な文章との違いを明確に打ち出せます。
読者の課題に寄り添った丁寧な解説や、業界ならではの実践的なアドバイスを入れることで、AIとの差別化を図りましょう。
クライアントに選ばれ続けるポイント
WebライターとしてAI時代に生き残るためには高品質な記事を継続的に提供できる信頼性が重要です。
まず納期を厳守し、クライアントのニーズを的確に把握することで、長期的な信頼関係を築くことが大切。
記事の質を保つため、AIツールを補助的に活用しながらも、人間らしい温かみのある文章を心がけましょう。
また、円滑なコミュニケーションを通じて、クライアントの要望を汲み取り、柔軟な対応を心がけることが大切です。





専門分野の知識をアップデートし続けることで、クライアントの期待に応える提案力も身につきますよ。
今すぐできるスキルアップ方法
AI時代に生き残るWebライターとして、実践的なWebライティングスキルの向上は重要です。
例として、以下の方法から始めると良いでしょう。
- 業界ニュースや最新トレンドのチェック
- SEO対策の基礎知識の習得
- 専門性を高めるための資格取得
- マーケティングの基礎知識の習得など
AIツールの使い方を学びながら、効率的な記事作成のワークフローを確立することも有効です。
さらに、ポートフォリオの作成や、自身のブログ運営を通じた実践経験の積み重ねも大切。
段階的なスキルアップを進めることで、AIに負けないWebライターとしての総合力を高められるでしょう。
WebライターのAIについてよくある質問
Webライターから多く寄せられるAI活用の疑問点として、以下のような内容がありました。
- 生成AIを使って書いた記事はバレますか?
- AIライティングは著作権的に問題ないですか?
- AIを使うとクライアントから単価を下げられますか?
それぞれの質問について順番に見ていきましょう。
生成AIを使って書いた記事はバレますか?
生成AIを使って書いた記事は、適切な編集を加えれば見分けることは難しいでしょう。
実際に、AIが生成した文章をそのまま使用すると、機械的で不自然な表現や、同じような言い回しの繰り返しが目立ってしまいます。
例えば、「なお」「また」といった接続詞の多用や、不自然な言い換え表現が特徴的です。
特に記事全体を通して人間らしい感情表現が乏しく、パターン化された文章になりがち。
ただし、AIの出力をベースに人間らしい表現を加え、文章の流れを整えることで自然な記事に仕上がるでしょう。





ほとんどのAIが無料で試すせるので、どんな文章になるのか実際に見てみましょう。
AIライティングは著作権的に問題ないですか?
Webライターが気になるAIライティングの著作権問題は、適切な使用方法を守れば問題ありません。
2025年1月現在、AI生成コンテンツに関する著作権法の整備はまだ発展途上の段階にあり、明確なガイドラインが確立されていない状況です。
ただし、既存の著作物を大量にコピーして学習したAIの出力には、著作権侵害のリスクが潜んでいます。
対策として重要なのが、AI出力の内容を必ず確認し、独自の視点や経験を追加することです。
AIはあくまでも文章作成の補助ツールとして活用し、最終的な編集責任はWebライター自身が持つという意識が大切でしょう。
AIを使うとクライアントから単価を下げられますか?
確かにAIの普及により、単純な記事作成の単価は下がる可能性があります。
しかし、AIの活用は、むしろWebライターの価値を高めるチャンス。
AIを効果的に使いこなすスキルを持つWebライターへの需要は、むしろ増加傾向にありますよ。
実際、多くの企業がAIを活用した効率的な記事作成に興味を持っている一方で、AIと人間のバランスが取れた質の高いコンテンツを求めています。
専門知識とAI活用スキルを組み合わせたWebライターは、高単価案件を獲得しやすい立場になりつつあるでしょう。
AIをうまく活用しながら独自の専門性や表現力を磨くことで、クライアントからの評価を高められる可能性も十分にありますよ。
まとめ:AI時代のWebライターに必要なこと
Webライター目線でAI活用のポイントをまとめると以下の通りです。
今回のまとめ
- AIは執筆の補助ツールとして活用し、完全依存は避ける
- AIは記事構成や情報収集で積極的に活用する
- クライアントのニーズに合わせてAI使用可否を判断する
- 専門性と表現力を磨いて、AIと差別化を図る
AIの登場により、Webライティングの効率は大きく向上させることが可能です。





ただし、AIはあくまでもツールの一つ。
人間ならではの経験や感情を組み合わせることで、より質の高いコンテンツを生み出せます。
まずは無料で使えるAIツールから試し、自分のライティングスタイルに合った活用方法を見つけてくださいね。