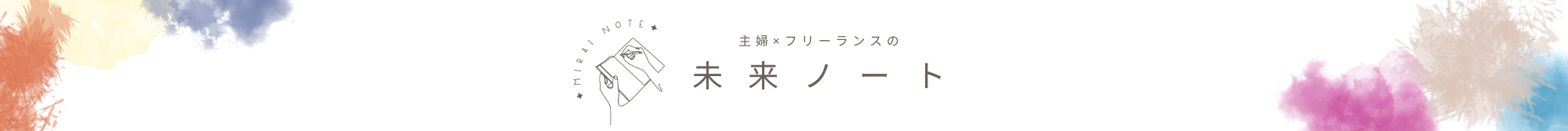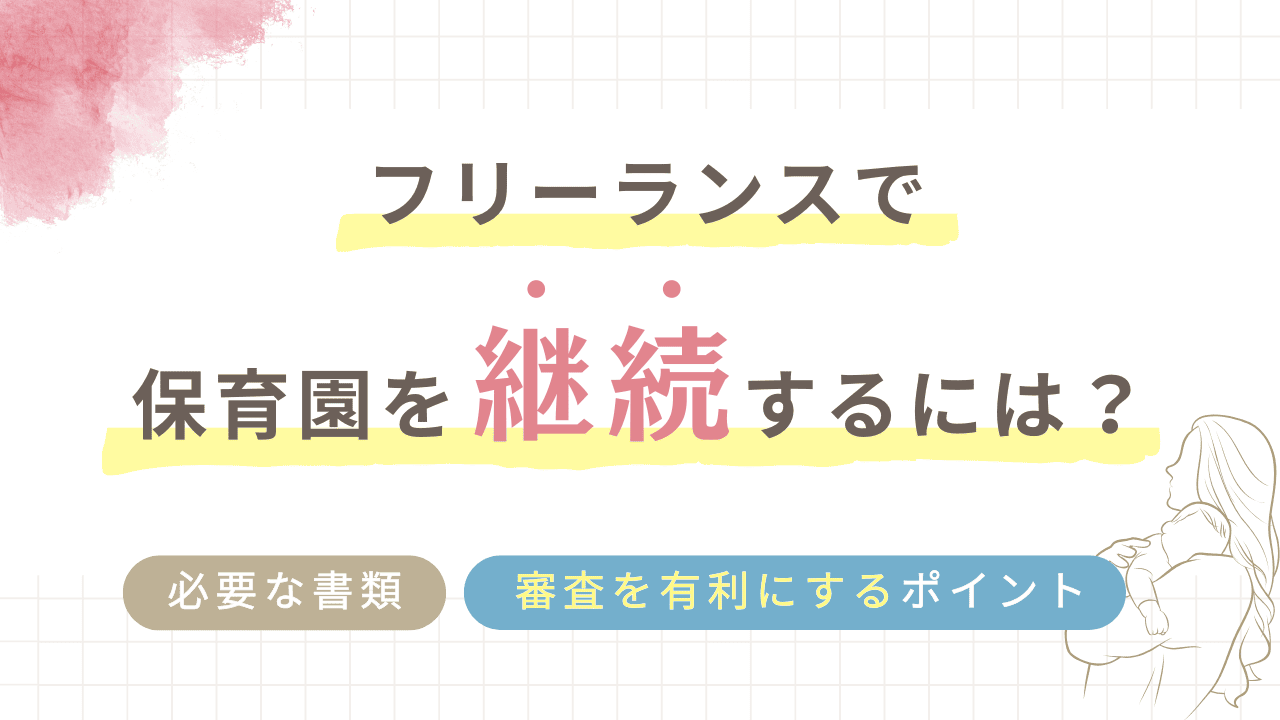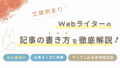理想の働き方を求めてフリーランスで活動されている主婦の皆さん。希望に胸を膨らませる一方で、お子さんの「保育園継続」について不安を感じていませんか?
特に会社員から働き方が大きく変わる場合、「今までと同じように預けられるのだろうか」「収入がなくても大丈夫?」といった疑問は尽きないでしょう。
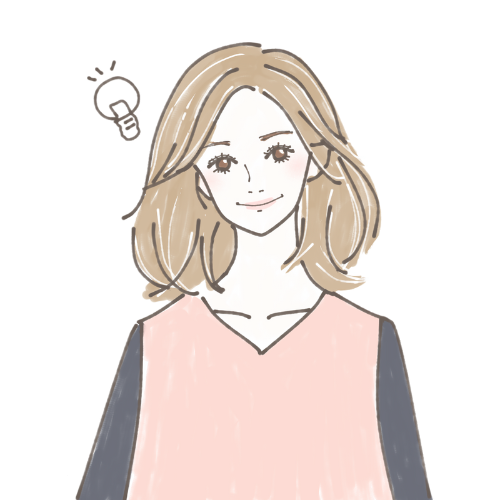
でも、安心してください。
結論から言えば、フリーランスになっても保育園の継続は十分に可能です。
しかし、会社員時代とは異なる独自のルールや証明方法があるため、事前の準備が成功の鍵を握ります。
この記事では、webライター、webデザイナー、グラフィックデザイナーなど、在宅でフリーランスを目指す主婦の方が、保育園をスムーズに継続するための具体的なステップと、心の不安を解消する情報をお届けします。
この記事で分かること
- フリーランスが保育園継続のためにクリアすべき基本的な条件
- 独立直後の「収入なし」の期間を乗り切るための具体的な証明方法
- 自治体の審査を有利にするための就労証明書作成の具体的なノウハウ
- 「自営業はズルい」という世間の目に対する正しい心構え
フリーランスになっても保育園は継続できる?結論と主婦が知るべき大原則
結論、フリーランスでも保育園の継続は原則可能です。
ただし、継続のためには自治体が定める「保育を必要とする事由」を証明し続ける必要があります。
会社員は、雇用契約・給与明細などで証明するのに対し、フリーランスは独自の書類で仕事の実態を証明しなければなりません。
- 保育の必要性の認定
- 自治体によるルール
- 会社員からフリーランス転身時の手続き
これらのポイントを理解することが、保育園継続の第一歩となります。
1. 継続の可否を決める「保育の必要性の認定」
保育園の利用は、児童福祉法に基づき、保護者が保育を必要とする場合に限られます。
働き方がフリーランスに変わっても、この「保育の必要性」が認められ続けるかどうかが継続の可否を決めるのです。
この認定に必要な条件は主に以下の2点。
- 就労時間(最低基準のクリア) …多くの自治体で「月64時間以上」の就労を継続していること。
- 仕事の実態(証明力) …実際に事業活動を行っていることを客観的な資料で証明できること。
これらは最低限必要となってくるでしょう。
2. 自治体によって異なる!フリーランスの保育園継続ルール
また、保育園の継続基準は、お住まいの市区町村によって大きく異なります。
特に、点数化される指数(基準指数)の計算方法が、会社員とフリーランスで差がつきやすい点に注意が必要でしょう。
例えば…
- 「自宅での就労」は「自宅外での就労」よりも指数が低い
- 開業届がないと「内職」扱いとなり点数が大幅減
などのケースがあります。
転身を考え始めたら、必ず自治体の保育課窓口に相談し、最新の継続利用基準を確認することが最優先事項と言えるでしょう。
3. 会社員からフリーランスへの転身時に必要な手続き
そして、会社を辞めてフリーランスとして独立する際は、速やかに以下の手続きを自治体に行う必要があります。
- 退職の報告と「就労状況変更届」の提出
- 新しい就労証明書(自営業者用)の提出
- 事業活動を証明する書類(開業届、業務委託契約書など)の提出
特に、会社を退職してからフリーランスとしての仕事が本格化するまでの期間では、次の章で解説する「収入なし」の期間に該当しやすいため、計画的な行動が求められますよ!
「収入なし」の独立直後が最大の不安!継続のために準備すべき実態証明とは?
フリーランスになり、独立直後や繁忙期と閑散期の差で一時的に収入がゼロでも、すぐに退園になるわけではありません。
保育園の審査で本当に重要なのは、「収入額」よりも「継続的な就労の実態」を証明できるかどうか、なのです。
webデザイナーなどの場合は特に納品までに時間がかかり、売上計上と実際の労働時間にズレが生じやすいものですが、この「労働の実態」をどう見せるかが継続の鍵となります。
- 労働時間と事業の持続性を証明する
- 実態を証明する資料
- 独立後の猶予期間
これらのポイントをひとつずつ解説しますね。
1. 審査で重視されるのは「労働時間」と「事業の継続性」を証明する
フリーランスや個人事業主の場合、審査側が特に確認したいのは以下の2点でしたね。
- 就労時間
- 事業の継続性
この2点を証明するためには、まず、1日のタイムスケジュール(タスク・時間)を具体的に作成し、保育がなければ仕事ができない状況を明確にすることが重要です。
2. 収入ゼロでも「仕事の実態」を証明する具体的な資料
収入がまだ発生していない、または低すぎる期間を乗り切るためには、将来の収入につながる「活動実績」を提出することが有効になってきます。
| 証明したい内容 | 提出すべき具体的な資料の例 |
|---|---|
| 事業の開始 | 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)の控え |
| 仕事の受注活動 | クライアントとの契約書、発注書、あるいは業務内容を話し合ったメールやチャットの履歴 |
| 納品・活動実績 | 制作物のポートフォリオ、ブログやウェブサイトの記事下書き、学習履歴(資格・スクール)、メルカリの販売履歴(事業として行っている場合) |
| 労働の記録 | 業務日報、タイムトラッキングツールの記録、カレンダーに記した具体的な業務タスクと時間 |
特に、メルカリやハンドメイド販売など、フリーランスの入り口となる活動をしている主婦の方は、それが単なる小遣い稼ぎではなく、「事業活動の一環」であることを示す資料を整理しておきましょう。
3. 独立直後の「猶予期間」を最大限に活用する
会社を退職した直後の場合は、求職活動を理由として、一時的に保育園の継続が認められる「猶予期間」が設けられている自治体が多いです。(期間は1~3ヶ月程度)
この猶予期間中に、以下のようなフリーランスとしての事業準備を完了させる必要があります。
- 開業届の提出
- 就労証明書の作成
- クライアントとの契約獲得など
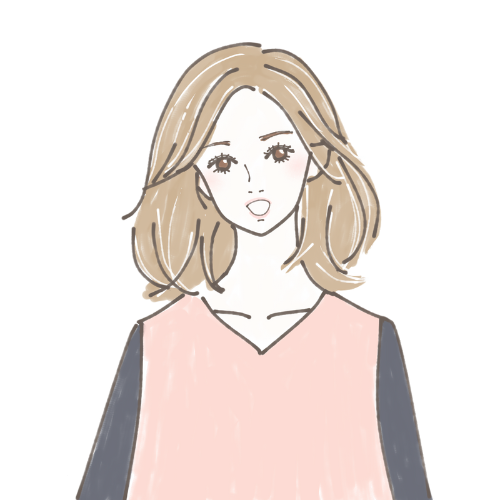
この期間は非常にタイトになるため、退職前から準備を進めておくのが得策ですね。
【開業届なしは不利?】フリーランスの就労証明書作成と審査を有利にするコツ
フリーランスの保育園継続手続きで、最も手間がかかり、かつ審査に直結するのが「就労証明書」の作成と、「仕事の実態を証明する資料」の提出です。
会社員は会社が発行してくれますが、フリーランスは全て自己責任で作成しなければなりません。
- 開業届の提出がおすすめ
- 就労証明書書き方のコツ
- 業務委託契約書があるとより安心
保育園の継続利用に有利になるポイントを解説していきます!
信用度が高まる「開業届」
「保育園 フリーランス 開業届なし」と検索される方も多いですが、結論から言えば、開業届がなくても保育園継続の申請は可能です。
しかし、フリーランスを目指す主婦には、開業届の提出を強くおすすめします。
| 開業届を提出するメリット | なぜ保育園審査で有利になるのか |
|---|---|
| 公的な証明になる | 税務署に提出した公的文書であり、「事業を開始した」という意志と事実を客観的に証明できる。 |
| 内職扱いを防ぐ | 開業届がないと、「お小遣い稼ぎ」や「内職」と見なされ、基準指数が低く評価されるリスクを避けられる。 |
| 青色申告ができる | 将来的に青色申告が可能になり、節税面でも有利になる。 |
開業届は税務署に提出するだけで、費用はかかりません。
▷ 開業届を準備できそうにない…という方は、こちらもチェック!
「開業届なしのフリーランスも保育園OKだけど…?注意点・代替書類・認定の気になること全部解説!」
自分で書く、就労証明書(自営業者用)の記入のコツ
また、保育園の利用に必ず必要な就労証明書は、あなたが「保育を必要とする時間」を証明する最重要書類です。
特に以下の点に注意して作成しましょう。
- 就労時間
- 仕事内容
- 自己証明の添付資料
✦ 就労時間の書き方
自治体の最低基準(例:月64時間、月120時間)を満たすように具体的に記載します。
自宅での作業時間であっても、「いつ、何をしていたか」を記録し、その合計時間を正直に記載してください。
✦ 仕事内容の具体性
「ライター」「デザイナー」といった職種だけでなく、「Webサイトの記事企画・構成・執筆」「クライアントのSNS用画像制作・ディレクション」などなど、具体的な業務内容を詳細に記載し、仕事の専門性と実態をアピールしましょう。
✦ 自己証明の添付資料
就労証明書が自己申告であるため、可能なら前述の契約書や業務メール、作業実績が分かる資料を添付し、証明書の記載内容に裏付けを持たせてください。
▷ 具体的な書き方は「就労証明書の書き方と準備」で解説しています◎
審査を有利に!業務委託契約書を準備する
webライターやデザイナーの場合、クライアント企業との「業務委託契約書」で、審査が有利に運ぶ可能性があります。
これは、第三者である企業が「あなたに継続的な仕事を依頼している」という事実を証明する最も強力な客観的資料となるからです。
もし契約書がない場合は、発注・受注のメールや、継続的な取引の実績が分かる請求書などで代替できますが、契約書があればよりスムーズに進むでしょう。
「自営業はズルい」の誤解を解く!正しく制度を利用するための心構え
それから、知っていますか?
実は「保育園 自営業 ずるい」というキーワードが検索されることも多く、フリーランスの保育園利用には、会社員から見るとネガティブな印象を持たれがちなこともあるんです。
しかし、あなたが後ろめたい気持ちになる必要は全くありません。
- なぜ「ずるい」と言われるのか?
- フリーランスが自信を持つ3つの心得
順番に見ていきましょう。
なぜ「ずるい」と言われるのか?その誤解の背景
「自営業はズルい」という批判は、主に以下の誤解や制度上の違いから生まれています。
| 批判される原因(誤解/不透明さ) | 批判の対象となっている事項 |
|---|---|
| 収入と労働時間の不透明さ | 会社員と違い、在宅で働くフリーランスは、他者から見ると「子どもを見ながら働けるのでは?」「本当に1日8時間も仕事をしているのか?」と思われやすい。 |
| 収入証明の差 | 収入が不安定な時期でも労働時間で保育園を継続できることが、「収入の低い会社員より有利」という誤解を生む。 |
| 保育料の決定基準 | 自営業者が保育料の面で優遇されているという誤解がある。 実際は、保育料は前年の世帯所得に基づいて決定されるため、収入が多ければ会社員と同様の保育料を支払っている。 |
自信を持って継続するための3つの心得
フリーランスの主婦が、後ろめたさを感じずに保育園を継続するための心構えは以下の通りです。
- 制度は正しく利用する
- フリーランスの保育の必要性を認識して
- あなたも、社会の担い手です
✦ 制度は正しく利用する
保育の必要性を証明するために、虚偽の記載は絶対にしないこと。
正当な手続きと、実際の労働時間に基づき申請することが大前提ですね。
✦ フリーランスの「保育の必要性」を認識する
自宅で行うフリーランスの仕事は、集中力が求められます。作業時間中は乳幼児の保育と両立は困難であることは、会社員と何ら変わりません。
正当な理由に基づき保育を利用していると自信を持ちましょう。
✦ 社会の担い手である自覚を持つ
フリーランスは、仕事を通じて社会に価値を提供し、適切に納税しています。
保育園は、働く親を支える社会制度であり、あなたもその恩恵を受ける権利を持っているのです。
▷ あわせて読みたい…「フリーランスの保育園が「ずるい」と言われる理由・解決策3選」
フリーランスで保育園を継続したい主婦からよくある質問
最後に、保育園継続に関して、フリーランスの主婦が抱きやすい疑問をQ&A形式でまとめました。
- 「フリーランスだから」と保育園継続を断られることはある?
- 求職中でも、保育園を継続利用できる?
- メルカリでの販売実績は、就労証明に使える?
それぞれ回答していきますね。
会社員からフリーランスになることで、それ自体を理由に継続を断られることはありますか?
フリーランスになったこと自体を理由に断られることはありません。
断られる(退園となる)のは、多くの場合、自治体が定める「最低就労時間」を満たせなかったり、「就労の実態」を証明する書類が不十分だったりする場合です。
フリーランスも自営による就労として、保育の必要性が認められる立派な事由です。
会社を辞めてすぐには仕事がない場合、求職活動中という形で保育園を継続できますか?
多くの自治体で「求職活動」は保育を必要とする事由として認められています。
ただし、これは一時的な猶予措置であり、自治体が定める期間(通常1〜3ヶ月)内に、フリーランスとしての開業届提出や具体的な就労証明の提出が求められます。
メルカリでの販売収入や実績も、就労証明として有効でしょうか?
事業として継続的に行っている場合は有効な資料となり得ます。
単なる不用品販売ではなく、
- 仕入れや作品制作
- 梱包、発送
- 顧客対応 など
事業としての労働時間を具体的に説明・記録した上で、販売履歴のスクリーンショットなどを提出すると、就労実態の裏付けとして機能する可能性が高いでしょう。
まとめ!保育園継続の鍵は「自治体への早期相談」と「仕事の実態の証明」
フリーランスという働き方は、時間に縛られず、場所を選ばない自由度の高さが魅力。
その一方、保育園の継続という観点からは、会社員時代とは異なる独自の準備が必要です。
このブログ「未来ノート」を運営する私たちも、主婦としてフリーランスの道を歩む皆さんの不安に心から共感しています。
保育園継続の成功に向けて、重要なポイントをまとめましょう。
今回のまとめ
- 継続は原則可能! ただし、自治体が定める最低就労時間(月64時間など)をクリアすること。
- 収入なしでも諦めないで。 重要なのは「収入額」ではなく「継続的な仕事の実態」を証明すること。
- 開業届は有利です! 仕事への本気度と社会的信用力を高める有効な手段となる。
- 就労証明書は具体的に。 自分で作成する就労証明書には、具体的な業務内容と労働時間を記録した裏付け資料を必ず添付する。
- 最も重要な行動は「相談」。 転身を決めたら、すぐに自治体の保育課窓口で継続条件と必要書類を直接確認すること。
これらの準備をきちんと行って、自信をもってフリーランスの道へ進みましょう。
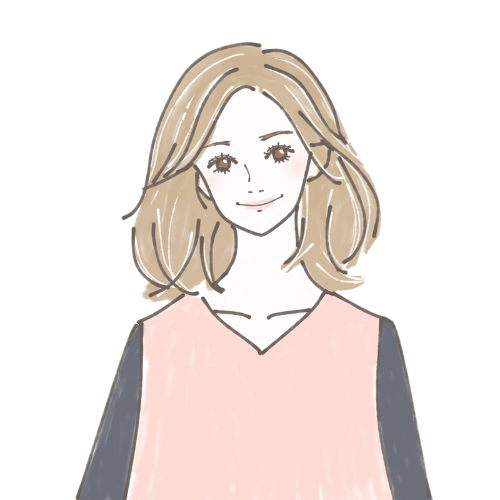
適切な準備と証明さえあれば、あなたのお子さんもこれまで通り保育園に通い続けることができます。
まずはお住まいの自治体の窓口や保育園へ、一歩踏み出して相談してみてくださいね。